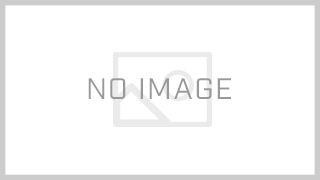はじめに
日本とタイは地理的にも歴史的にも異なる背景を持っていますが、不思議なほど似ている部分があります。それは「本音を抑えて調和を優先する」という文化です。
日本では「空気を読む」「忖度」といった言葉がよく使われ、タイには「クレンジャイ(เกรงใจ)」という独特の遠慮の概念があります。両者は似ているようでいて、その成り立ちや社会への影響には違いがあり、そこから両国の社会の姿が見えてきます。
日本文化 ― 空気を読む・忖度の社会
日本人は、集団の秩序や和を保つために「空気を読む」ことを重視してきました。会議の場で少数意見を飲み込み、周囲に合わせるのもその一例です。また、上司や権力者に対しては、言葉にされていなくても意向を推し量る「忖度」という習慣が根付いています。本来は思いやりの延長線上にあるものですが、組織や制度に深く入り込み、時に硬直を招いてきました。
その典型が、2023年から2024年にかけて明らかになった自民党派閥の不正資金問題です。長年、内部で問題を知りながらも「空気を読んで」指摘されず、最終的に大きなスキャンダルとして噴出しました。また、2024年から2025年にかけて報道されたフジテレビのセクハラ・パワハラ問題では、被害者が声を上げても組織が隠し続け、社会的な批判を受けてようやく責任が問われました。これらの事例は、日本において「空気を読む」ことが調和どころか不正や不祥事の温床になってきた現実を示しています。
タイ文化 ― クレンジャイと遠慮の社会
一方のタイには「クレンジャイ」という言葉があります。直訳すると「心に恐れを持つ」という意味ですが、実際には「相手に迷惑をかけないように遠慮する」という日常的な気遣いを指します。会議で反対意見があっても「難しいかもしれません」とやんわり伝えたり、上司を表向きには立てつつ、裏で不満を共有したりするのはその典型です。表では笑顔と礼儀を保ち、裏で本音を少しずつ伝えていく。そうした二層構造が、タイ社会の人間関係を滑らかにしているのです。
しかし、クレンジャイもまた制度に深く絡みつきます。2024年、改革派のMove Forward党は王室を保護する厳しい法律の改正を掲げ、多くの若者の支持を集めましたが、憲法裁判所はこの方針を「違憲」と判断し、党に撤回を迫りました。さらに、王室改革を訴えた活動家や人権派弁護士が実刑判決を受けるケースも増えています。若者は従来のクレンジャイを超えて声を上げていますが、制度の側がそれを跳ね返す構図が続いているのです。
比較と考察
こうして見てみると、日本とタイには「本音を抑えて場の調和を優先する」という共通点があります。どちらの社会でも、面子を守り、直接的な批判を避けることが礼儀とされます。ただし、その動機と影響には違いが見られます。
- 日本の「空気を読む・忖度」:集団全体の秩序と責任感から生まれ、結果として組織や制度を固めすぎてしまう。
- タイの「クレンジャイ」:相手個人への気遣いや人間関係の円滑さに根ざし、柔らかさがあるように見えるが、実際には権力構造を固める力として作用。
どちらも本来は「人を思いやる」文化ですが、行き過ぎれば社会の硬直につながります。日本では不正や不祥事の温床に、タイでは権力構造の固定に結びついているのです。
まとめ
日本とタイの比較から見えてくるのは、「遠慮」や「忖度」といった文化が人間関係を円滑にするだけでなく、社会のあり方そのものを形づくっているという事実です。
- 日本では空気を読むことが秩序と責任感を維持する一方で、不正を覆い隠す習慣となる。
- タイではクレンジャイが穏やかな人間関係を保つと同時に、権力者を守る仕組みとして働く。
両国に共通する課題は、この文化をどうバランスさせるかです。過剰になれば社会は硬直化しますが、適切に働けば人と人とをつなぐ潤滑油となります。
日本では少しずつ声を上げる動きが広がり、タイでは若者がクレンジャイを超えて変化を求めています。今後、両国の未来は「本音をどう社会に活かすか」にかかっていると言えるでしょう。